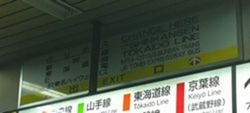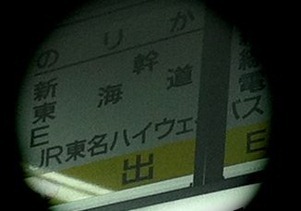朝起きたら、どこからともなく『Newスーパーマリオブラザーズ』の軽快なメインテーマが聞こえてきた。
「♪タラタラッ タッタッタラー タラタラ タッタタラー」
最近、『Newマリオ2』のコイン集めにドハマリしていたので、ついに幻聴が聞こえたか、と心配になった。しかし、それはピアノの音だった。下の階の子どもが一生懸命練習しているのだ。
マリオ。古今東西、世代を超えて楽しまれるキャラクタである。
「赤いオーバーオールを着た配管工のおっさん。」
「キノコを食べるとデカくなり、コインを集めまくるラテン系の陽気なヒーロー」。
こんな、聞いただけでわくわくするようなキャラクタが日本発だなんて、誇らしいよなぁ・・・
お布団にくるまりながら、そんなことを考えていた・・・
***
「消費者はハードを目当てに買うのではなく、ソフトをやるために仕方なくハードを買うのだ」というのは任天堂の名言である。
任天堂が常に業界の雄であり続けるのは、マリオを筆頭に、ポケモン、ゼルダ、ドンキーコング、その他革新的なキャラクタを載せたソフトウェアを、間断なく供給し続けてきたからである。
任天堂というのは、一見すると「ハードメーカー」でありながら、その実、ディズニーと並ぶ世界規模の「コンテンツホルダー」でもあるのだ。これはもっと国内で評価されていい。
これと闘っていると言われているのが、ソニーのPS陣営と、スマホの雄、アップルiOS陣営である。だが、ソニーもアップルも、最近の様子をみていると、どうもおかしい。
先ほどの言葉にすると、「消費者はハードを目当てに買う。ハードについてきたソフトウェアはおまけだ」と考えている節があるのだ。
だが、それは明確にまずい。どんなに高性能のハードでも、ソフトがなければただの箱、なのだ。
事実、当時最高性能を誇った「Nintendo64」は、発売当初のソフト不足が祟り(ファーストも含めローンチ後3か月間ソフトが出せなかった)、ハード競争で一時、PS陣営の後塵を拝することとなった。
古今東西、ハードメーカーのハードが売れてくるようになると、「自分たちのハードが素晴らしいから(売れる)」という錯覚に陥ってしまう傾向にあるようだ。しかし、その考え方の陥穽にハマってしまうと、途端に消費者からはそっぽを向かれる。
絶対に忘れてはならないのは、いかに「やりたいソフト」が揃うか、その1点なのである。かつてPS陣営が隆盛を極めたのはDQFFという「消費者がやりたいソフト」が揃ったからだ。
大容量のCD・DVD需要でPS陣営は一時、この世の春を謳歌した。しかし、やがて大容量化に伴う開発費の高騰化・ゲーム内容の複雑化により、従来のようにソフトウェアが売れなくなる(利ザヤが小さくなる)と、生き残りをかけてあらゆるサードパーティがマルチプラットフォーム戦略を取るようになった。Aというソフトを遊ぶのに、BというハードでもCというハードでもよい、というのがマルチプラットフォーム戦略だ。
ソフトメーカーにとっては、「データ」さえ作ってしまえば、ロイヤリティの負担だけで販売機会が拡大できるのだから、当然に選ばれる道だったのである。
すると、「このソフトを遊ぶには、このハード」という呪縛がなくなり、消費者の選択肢は大幅に広がっていった。畢竟、ファーストがどれだけ魅力的なコンテンツを用意できるか、ということにやがて話は収束していくことになる(ファーストが他のプラットフォームにコンテンツを供給することなど殆どあり得ないからだ)。
このタイミングで、「ゲーム人口の拡大」を掲げ、魅力的なファーストコンテンツを大量に集中供給することのできた「コンテンツメーカー」の任天堂は、驚異的な復権を遂げる。それは、苦境の時代にあっても、マリオ、ポケモン、その他良質なソフトウェアをコンスタントに供給するだけの開発力を維持してきたからこそ、の大偉業であった。
一方、サード頼みで自らが魅力的なコンテンツを大量に供給することが難しかった純然「ハードメーカー」たるSCEは、ハードの高性能化・先鋭化路線を取り、逆発展ともいえる状況を自ら生み出し、結果として両者の明暗を大きく分けることとなったのである。
魅力的なソフトウェアをそろえたプラットフォームが勝利する、ということは、マルチプラットフォーム時代においては、<ファースト自身が最大のコンテンツホルダーとならなければかなり厳しい展開を迫られる>、ということだ。それは、もはや歴史が証明した事実となりつつある。
否、現状はもっと厳しい。ファーストだけでなく、サードを実質セカンドパーティに近い形で取り込み、「このソフトウェアを遊ぶには、このハードでしかダメ」という状況を作ってしまわないとならないところまできている。サードをサードとして置いておけば、サードは少しでも利ザヤのある方に「いつでも寝返る」からである。
ファーストのコンテンツを充実させるのみならず、サードを実質セカンド化、ファースト化するという経営資源の徹底的な投入を図ってこそ、ようやく「コンテンツホルダー」として、プラットフォームを経営していくことができるのである。
まとめると、<ファーストとサードの融合的状況>を作ってはじめて、「売れるハード」を市場に出せる、そんな艱難極まりない状況が生まれつつある。
事実、サードパーティの中で現在、もっとも市場(ただし日本国内限定)から魅力的とされるコンテンツの1つである「モンハン」は、一時代前、PS陣営の屋台骨ともいえるソフトウェアであった。が、事実上、任天堂陣営への「完全鞍替え表明」が発生したことで、両者のハード戦争は決しつつある(かつてDQFFを根こそぎ奪われた任天堂の意趣返し、というのは言い過ぎか?)。
任天堂は、DQはじめ、モンハン、ソニック、その他、どんどん優秀なコンテンツを自陣営に引き込みはじめている。ファーストのみならず、サード陣営を強化(実質セカンド化)して、「ゲーム機サバイバル」に打ち勝たんとしている。それは何より、「ソフトの重要性」を熟知しているからこその動きに見える。
優秀なサードは(排除ではなく)取り込むに限る。せっかく、世界一優秀なGoogle地図とYoutubeというゴールデンアプリケーションを連動させていたiOSも(アップル自身がコンテンツホルダーとして動こうとした経緯はわかるにしても)、その超優秀なサードコンテンツを見事に「排除」した途端、今回の「地図騒動」である。
ハードは縁の下の力持ちでなければならない。重要なのは「どんなソフトを利用者に提供したいのか」ただ1点なのだ。
「こんなハードがあるから、こんなソフトを出す」のではなく、「こんなソフトを供給したいから、こんなハードを作る」という「あそび」の発想。これがあるからこそ、エンタテイメント企業である任天堂は「強い」のである。
***
・・・と、いうようなことを、朝の寝床で考えてみた。
朝はもう、9時になっていた。
公開:2012年10月8日